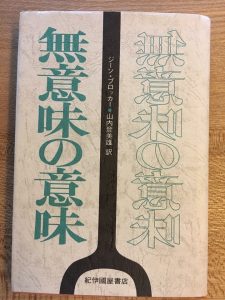不便益を「不便×益」足らしめている理由。それは多様な解釈です。
立ち位置により異なる価値観です。
・非効率であっても、非生産性ではない。
・不都合であっても、不必要ではない。
川上先生は、ここに不便益の原則があると述べています。
なるほど〜〜
非常にわかりやすい表現ですね。
「非」や「不」というネガティヴ要素から、そこに込めたい価値に対応する必要な根拠を見つめています。
こういった根源的な見つめかたは、人によって大きな「ゆらぎ」も起こします。
本当とは何か、とか、正しさとは何か、という深い議論にまで導かれることもあるでしょう。
このゆらぎ。
美術教育では、概念くずしなどで用いられます。
既成概念に疑問符を加え、違う切り口でとらえ直す考え方です。
たとえば、蛇口をひねったら水が出てくるのが当たり前です。でも、蛇口をひねったら鯨が出てきたらどうでしょう。
そんなもん、出てくるはずがない!
と言い出せば、楽しい発想は生まれません。
あり得ない! という感覚から新しい発想や構想を導き出す方法のひとつが概念くずしなのです。
なぜここで美術教育を引き合いに出すのでしょう。
それは、不便益には想像性と創造性の両方が必要だからです。
それを「芸術的な思考」というとらえ方もできます。芸術思考で有名な理論はアメリカの教育学者であるハワード・ガードナーの多重知能理論(MI理論)でしょうか。
この理論の中核にあるのは、「知能は単一ではなく、複数ある」「人間は誰しも複数(現在は8つ)の知能を持っている。長所やプロフィールが個人によって違うように、人によってある知能が強かったり、ある知能が弱かったりする」という考え方です。
複数の知能を組み合わせることであらたな思考をつくるのです。
なんだか不便益をつくるときのプロセスに似ていますね。
※〜※
さて、これまでを振り返ると結構な数の不便益のキーワードがでてきました。
前述の川上先生の言葉に意味や価値などの具体性を見つめる際は、おおよそ以下のようになるのではないでしょうか。
・柔軟な観点と遊びゴコロ
・二項対立より共通項探し
・判断対象は事態の背景から
・対象や作用に向かう態度
・随意性による概念くずし
・あなたにとっての必要性
あなたにとっての不便益、どう使ってみたいですか?
※今回の参考資料:多重知能理論の概要 恒安眞佐(芝浦工業大学)
http://sky.geocities.jp/society_of_mile/page007.html