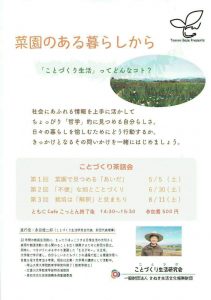「ことづくり生活」では世の中に絶対と言い切れることはないよね、という立場をとっています。
そのために考案したH.E.S.O.思考(へそ思考)は,「万能で常に答えが導ける」とは無縁です。単なる道具ですが,とても使い勝手の良い道具です。
そもそも初発の問いとは発する者の態度や立場に起因しますし、答えは普遍性のあるなにかというよりも、現実社会で探し得る共通了解的な「こと」だと考えています。また,そう考えないと永遠に見つけようのない超越的な世界観に埋没する可能性だってあります。
さて、今回はちょっと答えを探りようのない問いを発してみましょう。
こういう問いは言葉遊びと言われるのですが、案外大事なことが潜んでいます。
意味の意味を探る。
価値の価値を探る。
本質の本質を探る。
これは腹痛の腹痛とか愛の愛とは、と言っているのと同じで、文言自体をなぞれば堂々巡りを起こす問いです。だからと言って無用な問いだと言いたいのではありません。むしろ本質を探る大事なきっかけにもなり得て,ある意味とても哲学的な問いだと思っています。
これは「なぜ発したのか」を自分自身に問うところから始まります。次に発した言葉に込めた意味が立ち上がり、そして明確な具体性を得ながら全体が見渡せる位置を探る必要があります。
どこかに何かしらの答えが【ひとつ】ある。という前提だけで言葉のもつ意味をむやみに探っても、大事な本質を見落としてしまうことがあります。
今回の「意味の意味を問う」こと。
これ自体の問いと答えに重要な本質が隠れているというよりも、むしろそこに何が隠れているかを探る過程こそが大切だと考えてみましょう。というのも、この問いを発した者が「意味」という用語にどんな本質を求めているかに関わるからです。
そこで、本質には常に【3つ】の領域があるとみなすH.E.S.O.思考が活きてきます。
それでは、有名なリンカーンの名言をちょっと使ってみましょう。
「人民の人民による人民のための~」
おおっ,って心に響くような言葉ですが,これだって実は「人民」に込めた意味が漠然としていて、受け取る側の言葉に対する解釈が異なると意味も変わってきそうですよね。
それを例えば、出来事、仕組み、こころという順番で見つめてみましょう。
人民が作り出す「出来事」を、人民が作った「仕組み」によって、人民が「こころ」豊かに生活するための~
どうでしょうか。
また別のパターンを一つ。
「自由な自由を自由にする」
日本語としては支離滅裂ですけど、例えば「自由な思考という「仕組み」によって自由を感じる「こころ」を大切にして自由に「出来事」を生み出す」と組み直せば意味が通って来ます。
同じ言葉が繰り返されたとき、そこに込める意味なり価値をH.E.S.O.思考を使って見つめ直してみると、より具体的な方向が見えてくる場合もあります。
このように、へそ思考は支離滅裂になりがちな人との会話を整理するときにも使えますし、堅苦しそうな哲学的な問いに見えるような言葉にも具体性を提供できますし、超越的な話が得意な人の内容も整理することが可能です。
みなさんも普段使っている言葉にどんな事態などを込めているかを考えてみると、また違った視点が見つかるかも知れませんよ。
たまには童心にかえって無邪気に言葉遊びに興じてみてはいかがでしょうか。