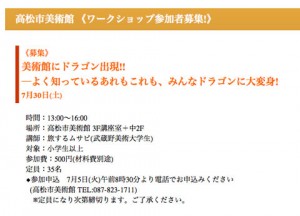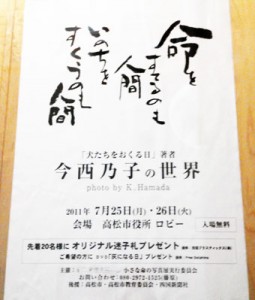これまで何気なく使って来た「感性」ということばについて、考える機会がありました。
まなびあい、について協力をお願いした先生より「定義が様々で、どう育ったかを判断することも立証することも難しい。感性が育つことは誰も反対しないし、できない。いいものだとはわかっていてもそれだけでは人を説得するのは困難ですよ」とご指摘を受けました。
自分でもぼかしたことばだなあ、と感じてはいても他に置き換わる言葉を探すこともなく、意味も深く考えなかったことに気づきました。ぼけたのが美術だと思わせてしまっていたなら、なおさらに「美術はどうでもいいや」の温床をつくってしまった原因なのかと自省しました。
私は何を込めたかったのかを考えてみました。
・感じ取る力を育てる
・関わり合う力を育てる
相手の思いを受け取り、自分の思いを土台にして相手に伝え、相手の意見を聞く。そして新しい価値をつくって行くたのしみを味わう。
美術=個人プレーの制作
ではないことを一般化しないと、結局制作できない人にとって特種性しか印象に残りません。だからこそ、「つながる」ということをキーワードに取り組まないといけないのでしょう。