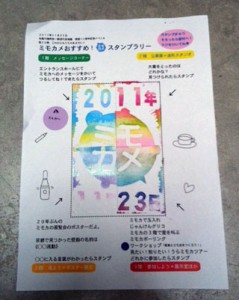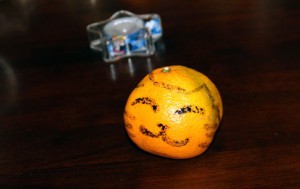写真を撮る愉しみというのもあります。
でも、今回紹介するのは香川県民文化大学でサンポートに言った際に、iPhoneでとったもの。
コンデジでも一眼でもないのですが、ちょい撮りに最近はiPhoneをよく使います。
広角なのでアップには出来ないんですけど、あとでトリミングすればいいかあ、と気楽にとってしまっています。

この数日前。強い風に悩まされていましたが、この日はおだやか。
空の色もばっちり。雲一つありません。そこでぱちり。
いい青でした。夏の瀬戸内海は白んだ青であまりきれいじゃありませんが、この日の青はとても透き通っていて素敵でした。

高速艇が水面を滑るように進んでいました。直島からのフェリーも入港して来ています。
空の青と生みの青、それに船の白さが際立って、とっても爽やかでした。

農場にて。この日はサンポートの前日。風がとっても強く、雲が勢いよく流れています。
ひまわりの葉っぱも風に吹かれてなびいています。
逆光ですが、真夏にしか撮影できないような風景が12月間際に撮影できる喜びです。

これも同日撮影。ホームページに使用するため加工しています。
春のようですが、これも11月下旬撮影という、季節を勘違いさせるように咲き誇るなのはなです。
一瞬を写し取る写真。そしてそこから想像する愉しみ。
写真って面白いですね。