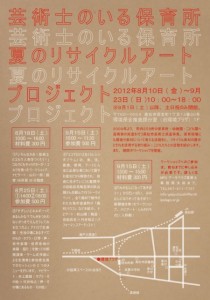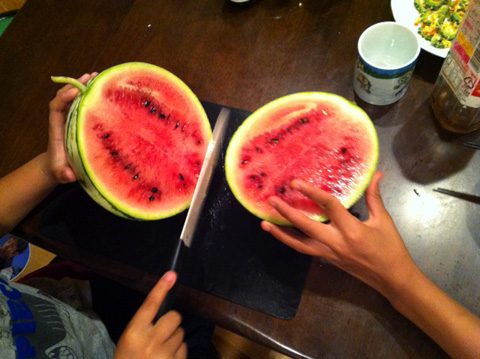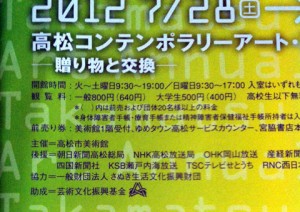7月21日(土)、13:40から東植田事業所にて第六回まなびあい勉強会を実施しました。今回の予定参加者は7名。1名は風邪でダウン、1名は自転車で来る予定でしたが、猛暑の中の移動がたたったのか、途中で熱中症になって帰宅。
とりあえず無事で何より。健康が第一です。みなさまもお気をつけくださいね。
ということで、今回も参加者5名のこぢんまりとした勉強会となりました。
初参加のメンバーも2名加わり、なかなか楽しい時間を過ごしました。
最初メンバーが揃わないので(迷子になって、、、わかりにくい場所で申し訳ない)施設案内をして、カフェスペースでのんびりくつろいでいると、勉強会のことはすっかり忘れて「まあ、いいか」という気分になってしまいました。
もっとも、そういう気分にさせてくれる施設を志向しているのですから、それはそれで非常にありがたい感想ですが、今日は勉強会のために集まったと言うことで、1時間遅れで勉強会をスタートしました。

今回の講師は、岡山大学大学院教育学研究科准教授の赤木里香子先生。美術教育史や美術館学をご専門に研究されています。その先生をお招きして「美術教育や美術館との出会い」を語り合い、美術教育の歴史について、実際の教科書を見ながらその時代の遍歴をお話しいただきました。
太政官布告で初めて登場した「美術」という文字。臨画から始まった図画教育が大正時代に山本鼎によって起こされた自由画運動、それに対抗して岸田劉生の鑑賞の大切さを訴える論が出ていく過程。教科書は図鑑の意味合いもあって、普段目にすることのない動物などを描いていた事実。戦前に使われていた教科書は戦後に黒塗り部分が多くなり、無教科書時代があったと言うこと。
そして私自身は、それらを現場にいるときにちゃんと学ばなかったこと。。。
現場の先生方にはこのあたりの歴史的事実をちゃんとふまえて、今どのような教育が必要かを考え、実践して頂きたいと感じます。
今回は中條財団の中條さんが参加され、お茶の話題がでました。
お茶も、その昔はそれ自体が展覧会であったこと、茶器などを通して会話をするスタイルであったことは、コミュニケーションを大切にしていると言うこと、そして道具はコミュニケーションの潤滑油として存在したこと。
お話を聞いていて、これらはまさに「対話による鑑賞」そのものではないかと感じました。戦国時代において一部の特権階級のものであったことは事実ですが、その時点から日本では「対話による鑑賞」が行われていたという事実は感慨深かったです。
岡倉天心の書いた「茶の本」を勧められましたのでアマゾンでポチッと購入。
まだ読めていないのですが、この夏の間には読んでおきたいと思います。